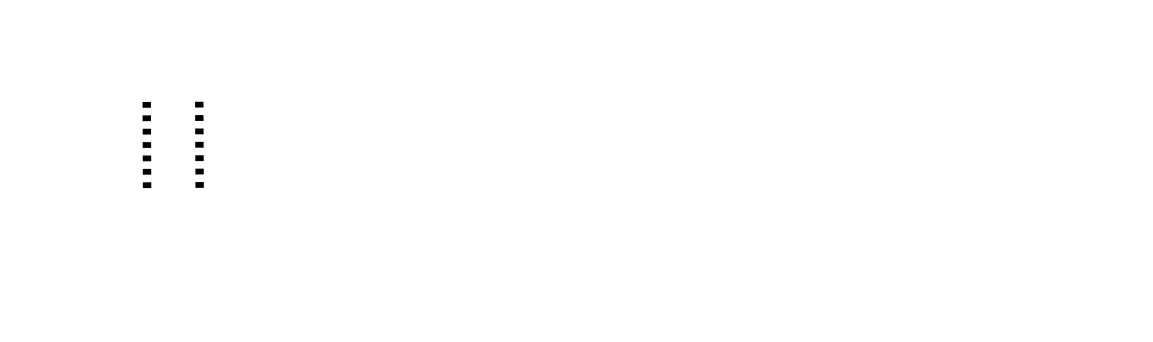過去の特集テーマ
2022年7月
2ヵ月連続! 隠れた傑作ホラーを
観る。掘る。もっと。
誰もが知っているような有名作ではないものの、みどころに溢れたレアなホラー作品を集めました。
マスター素材の紛失で長らく幻と言われていたが、素材が発見され再び陽の目を見たブルック・シールズの映画
デビュー作『アリス・スウィート・アリス』、 イタリアンホラー映画の巨匠ダリオ・アルジェント監督が
『サスペリア』『インフェルノ』に続いて描く“魔女三部作”完結編『サスペリア・テルザ 最後の魔女』、
ニュージーランドのホラー映画でその長い邦題でも話題となった
『マイドク』(略題)はHDマスター版をTV初放送!
この夏、見たことがある人もない人も、この奥深いホラーの世界にどっぷりハマってみるのはいかがでしょう?
放送作品ラインナップ
※放送当時の情報です。
 7/5(火)~7/8(金) よる 9:00~ 4日連続放送
/
7/5(火)~7/8(金) よる 9:00~ 4日連続放送
/
7/16(土)~7/17(日)よる 11:00~ 2日連続放送(全5作品)
-
7/5(火)よる 9:00 ほか
-
マイドク いかにしてマイケルはドクター・ハウエルと改造人間軍団に頭蓋骨病院で戦いを挑んだか
7/6(水)よる 9:00 ほか
-
7/7(木)よる 9:00 ほか
-
7/8(金)よる 9:00 ほか
-
7/8(金)よる 10:50 ほか
“日本語タイトル”に原題への忠実さは必要か
(解説・文/松崎健夫)
このようなことを話題にしているのには理由がある。それは、今回の特集で放送される作品にも、「タイトルの在り方」の様々なパターンを指摘できるからだ。例えば、ダリオ・アルジェント監督の『サスペリア・テルザ 最後の魔女』(07)。タイトルからも判るように、ダリオ・アルジェント監督による『サスペリア』(77)の続編的な作品だ。厳密には『インフェルノ』(80)を挟んだ<魔女三部作>の3作目で、完結編に位置する。だが、『サスペリア・テルザ 最後の魔女』の原題は、「Le Terza Madre」で「三番目の母親」という意味になる。つまり、“日本語タイトル”は原題と全く異なるものになっているのだ。そもそも、『サスペリア』における“日本語タイトル”の歴史にはいわくがある。『サスペリア』は日本で社会現象にもなった映画だが、その一端を担ったのは、作品そのものを観ていないであろう当時の子どもたちだった。テレビ番組「8時だョ!全員集合」で志村けんさんが、『サスペリア』のキャッチコピー<決して、ひとりでは観ないでください>を連呼して、爆笑をさらっていたからだ。そのブームにあやかって、配給の東宝東和は『サスペリアPARTⅡ』(75)を公開。原題を「PROFONDO ROSSO」=「深い赤」とするこのPARTⅡは、『サスペリア』の続編などではない。そもそも製作年が1975年であることからも判るように、『サスペリア』よりも前に製作された全く関連性のない作品を、日本ではPARTⅡとして公開させたのだ。現代の感覚からすれば、まさに炎上案件である。しかし、当時を知る映画ファンが激怒しているかというと、そうでもない。どちらかというと、斯様ないい加減さを楽しむような牧歌的雰囲気さえある。
『マイドク/いかにしてマイケルはドクター・ハウエルと改造人間軍団に頭蓋骨病院で戦いを挑んだか』(83)は、その長い“日本語タイトル”が公開当時話題となった作品。原題は「Death Warmed Up」=「死のウォームアップ」と、実にあっさりしたものだ。長い“日本語タイトル”を持つ映画の代表といえば、最長の記録を今なお保持するピーター・ブルック監督の『マルキ・ド・サドの演出のもとにシャラントン精神病院患者たちによって演じられたジャン=ポール・マラーの迫害と暗殺』(67)や、スタンリー・キューブリック監督の『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』(64)が挙げられる。『マイドク』は、その文脈から付けられた“日本語タイトル”なのだと解せる。監督のデヴィッド・ブライスは、後にハリウッドへ渡るも、『デビルジャンク』(89)の監督を撮影途中に解雇されたことで知られる人物。ニュージランド出身の彼は、当然『マイドク』の公開時は無名な存在。そもそもこの映画には、著名な俳優も出演していない。『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズのピーター・ジャクソン監督もニュージーランド出身の映画監督だが、『マイドク』はピーター・ジャクソンが日本に紹介される以前の作品。当時はまだ馴染みの薄いニュージランド製の映画に対して、話題を持たせるための作戦のひとつであったのだと推し量れる。そのインパクトある“日本語タイトル”のおかげか、『マイドク』は今なおカルト的な人気を誇っている。“日本語タイトル”に辿り着くまでの様々な事情を鑑みながら、今回の特集作品を観ると、「なるほど」と思える作品もあれば、「なんじゃこれは」と腰を抜かすような作品もある。そうやって原題と“日本語タイトル”との違いを調べ、楽しんでみるのも、また一興ではあるまいか。
写真:『マイドク いかにしてマイケルはドクター・ハウエルと改造人間軍団に頭蓋骨病院で戦いを挑んだか』(c) 1984 THE TUCKER PRODUCTION COMPANY LIMITED
スター・チャンネル×映画.com
コラボ企画
【マニアックホラー沼へようこそ】
激レア傑作、大放出ゾンビ映画世界選手権も開催!
この夏、涼しくなりたきゃここに行きやがれ! ~観なきゃ損な作品紹介~
映画.com「スターチャンネルEX 激レア!ホラー&ゾンビ
2022」ページへ
2022年8月
2ヵ月連続! 隠れた傑作ホラーを
観る。掘る。もっと。
誰もが知っているような有名作ではないものの、みどころに溢れたレアなホラー作品を集めました。
鬼才クローネンバーグ監督初期の傑作『ザ・ブルード 怒りのメタファー』や、
ソフト入手困難なアニマルパニック懐かしの秀作『ドッグ』など、
その他にも知られてはいないが、注目すべき見どころポイントを持った5作品を特集放送します。ぜひお見逃しなく!
放送作品ラインナップ
※放送当時の情報です。
 8/11(祝・木)~8/15(月)よる11:00頃~5日連続放送 /
8/11(祝・木)~8/15(月)よる11:00頃~5日連続放送 /
8/18(木)8/19(金)午後 1:50~ 2日連続放送(全5作品)
-
8/11(木)よる 11:40 ほか
-
8/12(金)よる 10:40 ほか
-
8/13(土)深夜 0:00 ほか
-
8/14(日)よる 11:10 ほか
-
8/15(月)よる 11:10 ほか
“二匹目のドジョウ”を味わう
(解説・文/松崎健夫)
いわゆる<動物パニック映画>は、『ジョーズ』以前から存在したジャンルだった。例えば、人喰い蟻との死闘を描いたチャールトン・ヘトン主演の『黒い絨毯』(54)や、アルフレッド・ヒッチコック監督の『鳥』(63)はその代表。とはいえ、『ジョーズ』の世界的ブームによって、<動物パニック映画>が粗製乱造されたという経緯に対しては、ほぼ異論が見当たらない。『ジョーズ』の公開によって生まれた<動物パニック映画>といえば、巨大な灰色熊が人間を襲う『グリズリー』(76)、シャチの復讐を描いた『オルカ』(77)、巨大タコが襲いかかる『テンタクルズ』(77)、遺伝子操作された殺人魚の恐怖を描いた『ピラニア』(78)、蜂の大群が急襲する『スウォーム』(78)などなど。例を挙げるとキリがないのだが、製作年を眺めると『ジョーズ』をきっかけにして、70年代にブームが起こったことが判るだろう。手を替え、品を替え、映画製作者たちが恥じらいもなく“二匹目のドジョウ”を狙った時代だったのだ。
そんな潮流の中で“二匹目のドジョウ”を狙って製作された『ドッグ』だったが、今なおカルト的な人気を得た作品のひとつとなっている。現在ソフトが廃盤となり、中古価格が高騰していることも、その隠れた人気を裏付ける証左だろう。『ドッグ』が異色な点はいくつかある。例えば、『ジョーズ』というよりも、むしろ『鳥』に近い構成になっている点。『鳥』では、映画の冒頭で鳥かごをサブリミナル的に見せることで、電話ボックスに閉じ込められたヒロインの姿に皮肉を込めていた。『ドッグ』でも、人間が部屋に閉じ込められてしまうプロセスを描くことで、同様の皮肉が劇中に流れている。また、<犬>同士がコミュニケーションを取り合っているかのような、“悟り”の表情を映し出す<モンタージュ>によって、不気味さを増幅させている点も秀逸だ。さらに、“犬視点”というトリッキーな映像で映画の幕が開ける点も挙げられる。『ジョーズ』の“サメ視点”という主観映像を、「犬の目線」=「超ローアングル」で実践することで、人間を不気味な存在に見せているのだ。
『ジョーズ』は「人間が巨大なサメに勝つ!」という鬼退治のような物語として幕を閉じるが、『ドッグ』はそうならない。『鳥』と同様に、犬が人間を襲い始める理由も正確には説明されない。そして、絶望的なラストショットも待ち構えている。実は、このラストショットに映る“あるもの”をモチーフにした続編が企画されていたが、叶わなかったという後日談もある。そのことが、ラストをさらに不気味なものにさせているのは、なんとも皮肉なことだ。ちなみに、今回放送される『デアボリカ』(74)も、『エクソシスト』(73)の“二匹目のドジョウ”を狙って製作されたイタリア製ホラー。よくよく考えると『ローズマリーの赤ちゃん』(68)の要素まで加わっている。ただし、(当時の感覚だと斯様な作品に出演するなど予想もしなかった)ジュリエット・ミルズの形相は、『エクソシスト』のリンダ・ブレアより恐ろしい!ともっぱらの評判だった。
写真:『ドッグ』(c) 1976 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
スター・チャンネル×映画.com
コラボ企画
【マニアックホラー沼へようこそ】
激レア傑作、大放出ゾンビ映画世界選手権も開催!
この夏、涼しくなりたきゃここに行きやがれ! ~観なきゃ損な作品紹介~
映画.com「スターチャンネルEX 激レア!ホラー&ゾンビ
2022」ページへ
2022年9月
日本VS世界のホラーを
観る。掘る。もっと。第3弾
ひと昔前は敬遠されていたホラー映画も今では恐怖の描き方が多様化し、
広く楽しまれる人気ジャンルとしての地位を獲得しています。
そんなホラーの中でも、今だからこそ注目したい「日本のホラー」と「世界のホラー」の見くらべ対決を
お届けする特別企画を昨年に続いて特集放送!
それぞれテーマは同じでも国が違えば表現方法も全く違う!
ぜひ見くらべてお楽しみください。
放送作品ラインナップ
※放送当時の情報です。
【 変身人間対決編 】
 9/3(土)夕方 5:20~ 一挙放送 /
9/16(金)よる 9:00~
9/3(土)夕方 5:20~ 一挙放送 /
9/16(金)よる 9:00~
一挙放送 ほか(全2作品)
【 おばけ屋敷対決編 】
 9/4(日)夕方 5:40~ 一挙放送
/9/22(木)よる 9:00~
9/4(日)夕方 5:40~ 一挙放送
/9/22(木)よる 9:00~
一挙放送 ほか(全2作品)
-
9/4(日)夕方 5:40ほか
-
9/4(日)よる 7:20ほか
(解説・文/松崎健夫)
そういった視点で<映画>と<怖いもの>との間には、もともと親和性があったことが判る。<ホラー>というジャンルは、<怖いもの>に特化したものとして、こちらも映画の歴史が始まって間もなく生み出されたジャンルだった。定説では1910年代以降のドイツ表現主義の作品群を源流とし、1930年代になってユニヴァーサル映画が量産した、ドラキュラやフランケンシュタインの怪物などの<モンスター映画>で確立されたとされている。また、<ホラー>というジャンル自体は小説の世界で先行していたこと、或いは、<見世物小屋>という場所における映画の視聴形態からも、親和性があったとも指摘されている。つまり、“驚き”や“恐怖”を訴求させる、お化け屋敷的な要素というのは、元々<映画>に備わっていたということなのだ。
一方、大林宣彦監督の長編デビュー作となった『HOUSE ハウス』は、<動物パニック映画>と無縁ではないという点が興味深い。この映画の製作当時、『ジョーズ』(75)が大ヒットしたことをきっかけに、世界的な<動物パニック映画>ブームが起きていた。そのため、シャチや巨大なタコなどに置き換えて、『ジョーズ』の亜流版とも言える作品が粗製乱造されたという経緯がある。実は大林監督も「家が人間を食べてしまう」という奇抜なアイディアを<動物パニック映画>から思いついたのだという。また、「屋敷に得体の知れない何かが取り憑く」という設定は、ダン・カーティス監督の『家』(76)やスチュワート・ローゼンバーグ監督の『悪魔の棲む家』(79)など、昔から製作されているが、『HOUSE ハウス』にはジャック・クレイトン監督の『回転』(61)を引用したような大林宣彦監督の映画的教養を感じさせるのも一興。
先日、取材でチェコ共和国を訪れた時のことだ。街を歩いていると、真っ赤なTシャツを着た現地の若者とすれ違った。なんとそれは、『HOUSE ハウス』のTシャツだったのである。アメリカのクライテリオン社から発売されたBlu-ray盤のパッケージが施されたインパクトあるデザイン。着ていた御本人が、どういうデザインであるのかを知っていたのかどうかはさておき、遠く離れたチェコの地で、まさか大林監督の『HOUSE ハウス』を目撃するとは夢にも思わなかったのだ。意外なことに、大林宣彦監督の作品は欧米で積極的にはソフト化されておらず、映画祭の場でレトロスペクティブ上映が行われるなどして、これから再評価が高まるのではないかという状況にある。そんな中でも『HOUSE ハウス』が、世界中で観られている作品であることを窺わせる余談である。
今回の特集には、もうひとつの見立てがある。それは、禁断のキノコを食した者の成れの果てを描いた『マタンゴ』(63)と、南極基地で孤立した隊員たちが地球外生命体と闘う『遊星からの物体X』(82)。日本とハリウッドの「変身人間対決」だ。この二本に共通するのは「一番怖いのは化け物ではなく、人間の方である」という真理。疑心暗鬼が人間の判断を狂わせてゆくメカニズムが、「人間ではいられなくなる」という恐怖によって描かれているのである。『遊星からの物体X』の原作「影が行く」は、ジョン・W・キャンベルが1938年に出版したもの。冷戦時代には『遊星よりの物体X』(51)として一度映画化されている。つまり、当時の赤狩りや冷戦へのメタファーとして、劇中の疑心暗鬼が「隣人は共産主義者なのではないか?」という疑心暗鬼へと繋がっていたというわけなのだ。
【出典】「現代映画用語事典」(キネマ旬報社)
写真:『HOUSE ハウス』(C)東宝 『マタンゴ』(C)東宝
スター・チャンネル×映画.com
コラボ企画
【マニアックホラー沼へようこそ】
激レア傑作、大放出ゾンビ映画世界選手権も開催!
この夏、涼しくなりたきゃここに行きやがれ! ~観なきゃ損な作品紹介~
映画.com「スターチャンネルEX 激レア!ホラー&ゾンビ
2022」ページへ
2022年10月
隠れた傑作ホラーを観る。掘る。もっと。
第3弾:『パペット・マスター』シリーズ一挙放送
誰もが知っているような有名作ではないものの、
みどころに溢れたレアなホラー作品を特集放送。
今回はカルトホラーの傑作シリーズとして人気の高い
『パペット・マスター』シリーズの
第1作~第3作を一挙放送。
第2作と第3作ではそれぞれ新たなパペットが登場するなどみどころも多く、
迫りくるパペットたちの恐怖に震えること間違いなし!
ぜひ一挙放送でお楽しみください。
放送作品ラインナップ
※放送当時の情報です。
【STAR2 字幕版】
 10/5(水)~10/7(金)よる
9:00~
10/5(水)~10/7(金)よる
9:00~
3日連続放送/10/22(土)よる 11:10~ 一挙放送 ほか(全3作品)
-
10/5(水)よる 9:00ほか
-
10/6(木)よる 9:00ほか
-
10/7(金)よる 9:00ほか
(解説・文/松崎健夫)
それだけではない、『悪魔のいけにえ』(74)のレザーフェイス、『ハロウィン』(78)のマイケル・マイヤーズ、さらには『エイリアン』(79)といったホラー映画のシリーズも、誕生した時代こそ1970年代だったが、シリーズ化されたのは1980年代になってからなのだ。ホラー映画の人気キャラクターが群雄割拠することで、『エイリアンVSプレデター』(04)や『フレディVSジェイソン』(03)など作品同士のクロスオーバーによる対決ものが企画・映画化されるなどに至ったことは周知の通り。
『パペット・マスター』シリーズを語る上で欠かせない人物がいる。それは、第1作で製作総指揮を担当したチャールズ・バンドである。彼は1983年に、ホラー映画を中心に映画製作を手掛けるエンパイア・ピクチャーズを設立。日本でも劇場公開されたスチュアート・ゴードン監督の『フロム・ビヨンド』(86)や、藤岡弘主演の『SFソードキル』(86)を製作したことで知られる映画会社だった。残念ながら、エンパイア・ピクチャーズは資金調達に失敗して短命に終わってしまう。その後、チャールズ・バンドが新たに立ち上げたフルムーン・エンタテイント(後に“フルムーン・フィーチャーズ”などに社名変更の経緯がある)で、ハリウッドメジャーのパラマウント・ピクチャーズと日本のパイオニア・ホーム・エンタテインメントとが組んで製作した最初の作品が『パペット・マスター』だった。
当時の経済界はソニーがコロムビア・ピクチャーズを、パナソニックがユニヴァーサル・ピクチャーズ(当時はMCA)を買収して、日本企業が「ハリウッドを買った」とアメリカ国内で非難された時代。また、日本ビクターが『プレデター』のプロデューサーであるローレンス・ゴードンと組んでラルゴ・エンターテインメントを設立したり、『ランボー/怒りの脱出』(85)などをヒットさせながらも経営危機にあったカロルコ・ピクチャーズに対してパイアニアLDCが追加出資するなど、日本とハリウッドの経営的な距離が近くなった時代でもあった。つまり『パペット・マスター』は、日本と無縁の作品ではなく、そのことがカルト的なファンを多く生んだ由縁のひとつだとも思わせるのである。チャールズ・バンド本人も『パペット・マスター』シリーズに思い入れがあるようで、シリーズ8作目『パペット・マスター/悪魔の人形伝説』(03)などで監督を担当している。
チャールズ・バンドの一族は、アメリカのエンタメ界と深い関わりがある。例えば、弟のリチャード・バンドは映画音楽家。『宇宙からのツタンカーメン』(82)や『バッフィ/ザ・バンパイア・キラー』(92)などの音楽を手掛け、兄チャールズとは『SFソードキル』や『プリズン』(87)など、数多の映画で組んでいる。そもそも、父親のアルバート・バンドは1950年代にラス・タンブリン主演の西部劇『ヤング・ガン』(56)でデビューした映画監督。息子チャールズが1970年代に映画製作会社チャールズ・バンド・プロダクションを設立した際、大手スタジオと縁のないインディーズ映画を配給する厳しい状況に対してアドバイスし、前述のエンパイア・ピクチャーズ設立時にハリウッド産業との橋渡しをした功労者でもあった。ちなみに、チャールズの息子であるアレックス・バンドは、「Wherever You Will Go」をヒットさせたロックバンド“ザ・コーリング”のボーカルだったりする。
現在『パペット・マスター』は、前年に公開された『チャイルド・プレイ』(88)のヒットにあやかった、小さな殺人者の系譜にあたる作品だと評されている。だが果たして、本当にそうなのだろうか?『チャイルド・プレイ』の前年、チャールズ・バンド率いるエンパイア・ピクチャーズは、犯罪者の魂を封印した人形が登場する『ドールズ』(87)を製作している。さらに、チャールズ・バンド・プロダクションで製作した『デビルズ・ゾーン』(79)の舞台はカラクリ人形館だった。そして、『デビルズ・ゾーン』を監督したのは『パペット・マスター』のデヴィッド・シュモーラーだったりもする。『パペット・マスター』が『チャイルド・プレイ』の亜流版などではない、とする筆者の見立ての証左のひとつなのである。
【出典】『パペット・マスター』
公式サイト https://www.puppetmaster.jp/
スター・チャンネル×映画.com
コラボ企画
【マニアックホラー沼へようこそ】
激レア傑作、大放出ゾンビ映画世界選手権も開催!
この夏、涼しくなりたきゃここに行きやがれ! ~観なきゃ損な作品紹介~
映画.com「スターチャンネルEX 激レア!ホラー&ゾンビ
2022」ページへ
2022年11月
東南アジア発!空前絶後のアクション映画特集
そんなイメージとはちょっと異なる東南アジアの新時代アクション映画3作品を特集放送。
プラスアルファの要素で見ごたえが増した東南アジア発アクション映画をぜひお見逃しなく!
放送作品ラインナップ
※放送当時の情報です。
【STAR1 字幕版】
 11/7(月)~11/9(水)よる
9:00頃~
11/7(月)~11/9(水)よる
9:00頃~
3日連続放送(全3作品)
-
11/7(月)よる 9:15 ほか
-
11/8(火)よる 9:15 ほか
-
11/9(水)よる 8:45 ほか
(解説・文/松崎健夫)
例えば、『リング』(98)や『呪怨』(00)などのJホラー、『the EYE【アイ】』(02)や『Mirror 鏡の中』(03)、『心霊写真』(04)などのアジアで製作されたホラー映画が、立て続けにハリウッドで映画化されたように、フィリピン製のホラー映画『SIGSAW』(08)も斯様な潮流の過程でハリウッドにて映画化されたという経緯がある。その点で『牢獄処刑人』は、アクション場面もさることながら、犯罪映画としての秀逸な設定が評価されているのが特異なのだ。
第66回カンヌ国際映画祭の監督週間で上映された『牢獄処刑人』は、高い評価を受けたことから、まずは北米での配給・上映につながってゆく。その後、ハリウッドで映画化権が獲得され、『ビースト』(22)のバルタザール・コルマウクル監督によるリメイクがアナウンス。だが、企画は長らく進展せず、現在に至るまで映画化されていなかった。獲得された映画化権が寝かされたままになることは、『AKIRA』実写化などの例があるようにハリウッドではよくある話。だが、エリック・マッティ監督は諦めなかったのである。
2021年にHBOのミニシリーズ(厳密にはHBO Asiaでの製作)として自ら映像化。本来は続編として企画していた「On the Job:Missing 8」(21)を、6話構成、208分の作品として完成させたのだ。劇場公開を予定していたものの、コロナ禍のパンデミックで映画館が閉鎖。一時はリリースの危機に直面した。そんな時、ワーナーメディア・アジアが配給権を獲得したことで、奇しくもミニシリーズとして再編集されることになったのだ。この作品は第78回ヴェネチア国際映画祭でお披露目され、会場のスタンディングオベーションで迎えられている。事件を追うジャーナリストの視点で描かれた「On the Job:Missing 8」の1話と2話は、『牢獄処刑人』を再編集したうえで、映像がリマスターされている。
フィリピンの映画界では、『立ち去った女』(16)のラヴ・ディアス監督や『ローサは密告された』(16)のブリランテ・メンドーサ監督のように、ヴェネチアやカンヌなど国際映画祭の場で評価されている映画人も存在する。『ミッドナイト・アサシンズ』のミカイル・レッド監督も、第29回東京国際映画祭で『バードショット』(16)が上映され、アジアの未来部門で作品賞に輝いている逸材。『ミッドナイト・アサシンズ』は、『ネオマニラ』のタイトルで第13回大阪アジアン映画祭のコンペ部門に選ばれ、<来るべき才能賞>を受賞している。
意外に思えるかも知れないが、フィリピンは世界の上位に入る映画大国のひとつ。国内では毎年150本前後の映画が製作されている。つまり、毎週3本〜4本の新作映画が劇場公開されている計算になる。この本数は約170本前後の映画を毎年製作しているイタリアやメキシコに近く、ロシアやオーストラリアよりも多い。先述のラヴ・ディアズ監督やブリランテ・メンドーサ監督の作品は 近年ほとんどの映画が日本でも劇場公開されるようになった一方で、キャシー・ガルシア・モリーナ監督のようにフィリピン本国で人気の監督作品はほとんど紹介されてないという現実もある。日本で劇場公開されるフィリピン映画は毎年僅か数本なのだ。
とはいえ、『牢獄処刑人』には脚本のクレジットに“ミチコ・ヤマモト”という名前が確認できるように、日本との繋がりも指摘できる。彼女は日系フィリピン人の脚本家で、現在はエリック・マティ監督夫人でもあり、「On the Job:Missing 8」にも参加している。余談だが、1977年に日本で放送されたアニメ「超電磁マシーン ボルテスV」が、約半世紀を経てたフィリピンで、現在テレビ向けの実写リメイクを撮影している。フィリピンでは1978年に放送され、視聴率58%を記録した人気番組だったという。実は、筆者がいま一番見たい作品のひとつだったりするのである。
「世界の統計2022」総務省統計局
https://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.htm
スター・チャンネル×映画.com
コラボ企画
【マニアックホラー沼へようこそ】
激レア傑作、大放出ゾンビ映画世界選手権も開催!
この夏、涼しくなりたきゃここに行きやがれ! ~観なきゃ損な作品紹介~
映画.com「スターチャンネルEX 激レア!ホラー&ゾンビ
2022」ページへ
2022年12月
「ハル・ハートリー監督を観る。掘る。もっと。」
1992年に『シンプルメン』、翌年にはその前作『トラスト・ミー』が
日本で初めて公開され、日本の映画ファンを虜にしたハートリー監督。
ニューヨークのインディーズ映画の中ではジム・ジャームッシュなどと比べると日本での知名度は高くないものの、
ジャームッシュとは異なる「郊外」の地方都市を舞台に、普通の若者を軸にした映画を撮ったことで、
多くの若者たちからの共感を得て熱い支持を受けた。
彼の映画のポイントのひとつで、監督自身が手掛ける音楽もあわせてハートリー監督作の魅力をぜひご堪能ください!
放送作品ラインナップ
※放送当時の情報です。
【STAR2 字幕版】
 12/3(土)~12/4(日)夕方6:30頃~ 2日連続放送/
12/3(土)~12/4(日)夕方6:30頃~ 2日連続放送/
12/19(月)~12/24(土)よる9:00~ 6日連続放送(全6作品)
(解説・文/松崎健夫)
一方で、ニューヨークのある東海岸は、同じアメリカとはいえ事情が異なる。西海岸には映画産業が興って以来、ワーナー・ブラザースやパラマウントなどのメジャースタジオがいくつも存在するが、東海岸にはハリウッドほど多くの映画会社は存在しないからだ。勿論、ハリウッド映画を東海岸で撮影することはあるものの、製作本数は西海岸ほど多くはないという実情がある。製作本数がハリウッドに比べて少ないことは、映画を撮影するスタジオの数、撮影機材を貸し出す業者の数、さらには映画出演を望む俳優の数(或いは資質)に影響を及ぼすことになる。つまり、スタジオ撮影が難しいことはロケ撮影を多用することに繋がり、機材の手配が難しいことは限られた機材を駆使した手法を生み出すことに繋がる。そして、映画出演経験のあるプロの俳優があまりいないことは、舞台俳優(ニューヨークであればブロードウェイ出身)や素人を役者に起用するという選択を導いてゆく。このような要素が集積することで、奇しくも東海岸出身の監督たちが生み出す映画の“スタイル”が生まれていったのである。
ハル・ハートリーは東海岸を拠点とする映画監督のひとり。ニューヨーク州に生まれ、1980年代にニューヨーク州立大学パーチェス校で映画製作を学んだことは、映画における彼の“スタイル”を生み出した源泉なのである。ハートリーの作風は「ミニマムである」と評されてきた。それは、最小限のショットを繋ぎ合わせ、登場人物たちの内面をあぶり出すことに長けていた点に由来する。技巧的な構図やカメラワークを駆使するのではなく、平面的でシンプルなショットを積み重ねながら音楽を乗せてゆく。斯様な簡約さが監督作品で貫かれていたことは、やがてハル・ハートリーの“作家性”となったという経緯がある。また、彼は脚本を兼任するだけでなく、編集を手掛けたり、ネッド・ライフル名義によってハートリー自身が音楽を担当するといった自由さもある。ハートリーは『トラスト・ミー』(90)でサンダンス映画祭の脚本賞に輝いたことを機に、いちやく東海岸出身の若手注目監督へと躍り出るのだ。
ハリウッドではインディペンデント映画とはいえ、俳優や監督、スタッフたちが加入する組合の規約に基づいた制約がある点も重要だ。俳優であれば、ハリウッド映画での出演歴を基準とした映画俳優組合(SAG)の組合員であることが、映画出演の条件であったりするからである。その点でハル・ハートリーは、大学の同期であるロバート・ジョン・バークを『シンプルメン』(92)の主役に起用している。バークはハートリーとのフィルモグラフィを活かすことで、ピーター・ウェラーが降板した『ロボコップ』シリーズのロボコップ役を『ロボコップ3』(93)で演じることとなり、ハートリーの『FLIRT/フラート』(95)にも出演。インディペンデント映画には制約がないこともまた、ハートリーの作風を生み出した由縁のひとつだと言えるだろう。
1990年代以降のハリウッドでは、税金の優遇措置を求めてカリフォルニア州以外のロケ地を求めるようになったが、それはハートリーが映画製作をしていた少し後の時代のこと。彼が故郷であるニューヨークを拠点にし、作品にニューヨークの風景が記録されていることもまた、彼の“作家性”を導く理由のひとつとなっているのである。ちなみに、先述のコッポラやルーカス、さらにはスティーヴン・スピルバーグと同時期に東海岸で映画製作をしていた監督たちに、『タクシードライバー』(76)のマーティン・スコセッシや、『アンタッチャブル』(87)のブライアン・デ・パルマたちがいる。彼らは映画製作において、アメリカの西海岸と東海岸で切磋琢磨し合う若手監督同士だったのだ。
同様に、ハル・ハートリーの同時代には、『ストレンジャー・ザン・パラダイス』(84)のジム・ジャームッシュや、『キング・オブ・ニューヨーク』(90)のアベル・フェラーラといった東海岸を拠点とする映画監督が活躍していたという時代性もある。これらの潮流は、ニューヨークを拠点に個性的な映画を製作・配給している映画会社A24の存在とも無縁ではない。思い起こせば、映画製作にとってまだ荒地であった1950年代後半に、ジョン・カサヴェテスが『アメリカの影』(59)の製作をはじめたのもニューヨークだった。ハリウッドで活躍する俳優であったカサヴェテスが、故郷であるニューヨークで自由な映画製作を試みたことは<インディペンデント映画の父>と呼ばれる由縁。その精神がハル・ハートリーの監督作にも漲っているのである。
スター・チャンネル×映画.com
コラボ企画
【マニアックホラー沼へようこそ】
激レア傑作、大放出ゾンビ映画世界選手権も開催!
この夏、涼しくなりたきゃここに行きやがれ! ~観なきゃ損な作品紹介~
映画.com「スターチャンネルEX 激レア!ホラー&ゾンビ
2022」ページへ
2023年1月
知られざる驚きの実話映画を観る。掘る。もっと。
知られざる驚きのストーリーが描かれる映画6作品を特集放送!どうぞお楽しみに!
放送作品ラインナップ
※放送当時の情報です。
【STAR1 字幕版】
 1/8(日)ひる
12:00~ 一挙放送/
1/8(日)ひる
12:00~ 一挙放送/
1/16(月)~1/20(金)よる 9:00頃~ 5日連続放送(全6作品)
-
1/8(日)よる 9:00
1/17(火)よる 9:00 ほか -
1/8(日)よる 11:00
1/20(金)よる 9:00 ほか -
1/8(日)午後 2:15
1/16(月)よる 8:30 ほか -
1/8(日)夕方 4:45
1/19(木)よる 9:00 ほか -
1/8(日)夕方 6:45
1/18(水)よる 8:30 ほか -
1/8(日)ひる 12:00
1/20(金)よる 10:45 ほか
(映画評論家・松崎健夫)
また、お隣の韓国では、『パラサイト 半地下の家族』(19)がカンヌ国際映画祭で最高賞に輝き、アカデミー賞でも作品賞に輝くなど、批評的にも興行的にも国際的な成功を収めている印象がある。しかし、その根底にも国外マーケートへの意識が指摘できる。例えば、韓国の総人口が5147万人(2021年の統計)であることは、日本の人口の半分にも満たないことを意味する。つまり韓国においても、国内のマーケットだけでは潤沢な資金を製作費に投入する裏付けが乏しいのだ。映画のみならず、テレビドラマや音楽の世界においても国際的な人気を掴んだ韓国のエンターテインメント界。斯様な成功に対して羨望するような報道を日本のメディアでは散見するが、そこには地政学的な問題も介在しているのである。
ふたつめは、何らかの<原作>があることが、興行収入に対する裏付けを示せるという点が挙げられる。例えば、小説や漫画が原作となっている場合。書籍の発行部数は、おおよその購買者や読者の数でもあるため、映画化した際の観客動員を予想しやすくなるデータに変換される。またテレビドラマであれば、視聴率がその参考になり得るだろう。その点でオリジナル脚本は、観客動員を予想・算出するための裏付けに乏しいのだ。今回の特集では「知られざる驚きの実話」を映画化した作品がラインナップされている。この<実話>というモチーフもまた、観客動員の裏付けとなっている点が重要なのである。
『ゴヤの名画と優しい泥棒』(20)は、1961年にロンドンの国立美術館からフランシス・デ・ゴヤの名画が盗まれた実際の事件を描いた作品。後半は裁判劇となるのだが、超法規的とも解釈できるような粋な判決のゆくえは、約50年前の出来事ながら痛快だ。また、『クーリエ:最高機密の運び屋』(20)は、<キューバ危機>の回避に貢献したスパイの知られざる真実を描いた作品。スパイ経験のないイギリス人セールスマンが、核戦争勃発を阻止したという紙一重の事実には驚愕するばかりだ。ラインナップのうち、『ドリーム』(16)や『モーリタニアン 黒塗りの記録』(21)は、映画化の際に基となったノンフィクションや手記などの<原作>があるのだが、『ゴヤの名画と優しい泥棒』と『クーリエ:最高機密の運び屋』には原作となるものがない。重要なのは、<実話>だという点にある。
<実話>には、新聞や雑誌で記事になり、話題となったものも多い。つまりこのことは、小説や漫画のような<原作>同様の“知名度”を導き、企画にゴーサインを出すか否かの判断材料になっているのである。例えば、『クーリエ:最高機密の運び屋』のように、<キューバ危機>という歴史的事実を題材にしながら、そこへ「知られざる事実」が付加されることで、たとえ書籍化されてなかったとしても、<実話>そのものの“知名度”を観客動員の裏付けとする事例があるのだ。加えて、ISISとSWATとの市街での攻防戦を描いた『モスル あるSWAT部隊の戦い』(19)のように、雑誌「ニューヨーカー」に掲載された記事を原案に映画化したという特異な経緯まである。ハリウッド映画には、存命の政治家を描く(日本では映画化困難と思えるような)作品が存在するが、これらの作品は「たとえ存命の人物であっても、記事が原案であれば映画化できる」というロジックによって製作されてきた背景もある。
アカデミー賞では、映画のために書かれたオリジナル脚本に対する<脚本賞>と、小説や戯曲、ノンフィクションなどの原作を基にした脚本に対する<脚色賞>があり、明確に部門が分けられている。そもそも日本映画界だけでなく、実はハリウッド映画界においても「ネタ不足」と言われて久しいという現状もある点も重要だ。過去10年の北米年間映画興行ベストテンを俯瞰すると、マーベルやDCのアメコミ作品、シリーズ物などの続編、或いは、リメイク作品ばかりがランキングされていることが判る。『ズートピア』(16)などのピクサー作品を除くと、実写では『TENET テネット』(20)や『ゼロ・グラビティ』(13)くらいしか(原作のない)オリジナル脚本の作品は見当たらない。その危機感こそが、(原作のない)<実話>に目が向けられている由縁でもあるのだ。
スター・チャンネル×映画.com
コラボ企画
【マニアックホラー沼へようこそ】
激レア傑作、大放出ゾンビ映画世界選手権も開催!
この夏、涼しくなりたきゃここに行きやがれ! ~観なきゃ損な作品紹介~
映画.com「スターチャンネルEX 激レア!ホラー&ゾンビ
2022」ページへ
2023年2月
『スペンサー ダイアナの決意』&『プリンセス・ダイアナ』
独占プレミア放送記念特集映画が描いた英国王室
ドキュメンタリーも含め、様々な時代のドラマティックな英国王室の世界描いた全8作品をお届けします。
放送作品ラインナップ
※放送当時の情報です。
 2/18(土)~2/19(日) 2日連続放送/
2/18(土)~2/19(日) 2日連続放送/
2/21(火)~2/24(金)午後 2:00頃~ 4日連続放送(全8作品)
-
2/18(土)よる 9:00 ほか
-
2/18(土)よる 7:00 ほか
-
2/18(土)午後 3:15 ほか
-
2/18(土)夕方 5:15 ほか
-
2/19(日)ひる 12:45 ほか
-
2/19(日)午後 3:00 ほか
-
2/19(日)夕方 5:15 ほか
-
2/19(日)夕方 6:15 ほか
-
2/19(日)よる 7:15 ほか
(映画評論家・松崎健夫)
『スペンサー ダイアナの決意』は、1991年が舞台。クリスマスに王族が集まるエリザベス女王の私邸で、ダイアナが離婚を決意する3日間が描かれている。この映画では、劇中の音楽に演出の特徴を見出せる。例えば、劇伴の使い分け。ダイアナが家族と過ごしている場面では、劇伴がクラッシック調であるのに対して、彼女がひとりですごしている場面ではジャズ調になっているのだ。斯様な演出は、ダイアナを取り巻く環境に二面性があることを、視覚的な要素だけでなく音響によっても表現して見せていることを窺わせる。また、映画終盤に子どもたちを連れて私邸を去るダイアナが車の中で聴いている、マイク&ザ・メカニクスの楽曲「ミラクル」も印象的だ。1986年に発表されたこの曲は、全米チャートで5位を記録したヒット曲。映画の舞台は1991年なので、少し前のヒット曲を聴いているという設定であることが判る。<必要なのは奇跡だけ>と歌われる「ミラクル」(原題はAll I need is a miracle)は、まるでダイアナの心情を代弁しているかのようなのだ。それだけではない。この曲がヒットしていた当時、チャールズ皇太子の外泊が増え、家族がバラバラになり始めた時期と重なるのだ。この場面でダイアナが想うのは、未来へ望む奇跡なのか、それとも、別居に至った過去の苦い思い出なのだろうか。
マイク&ザ・メカニクスは、ロックバンド“ジェネシス”のメンバーであるマイク・ラザフォードによるソロ・プロジェクト。ジェネシスは、初代ボーカルのピーター・ガブリエルが脱退し、1978年には9thアルバム「そして3人が残った」を発表して3人体制になっていた。マイク&ザ・メカニクスの活動が始まった頃、ジェネシスのメンバーはバンドを離れて、個々の活動を行なっていた時期でもあったのである。例えば、トニー・バンクスはケヴィン・ベーコン主演の『クイックシルバー』(85)で音楽を担当。フィル・コリンズはソロ活動が成功して、『カリブの熱い夜』(84)の主題歌「見つめて欲しい」が全米チャートで1位を記録。アカデミー賞では主題歌賞の候補になっていた。そんなジェネシスは、フィル・コリンズの活躍も伴って、13thアルバム「インビジブル・タッチ」が1500万枚を売り上げる世界的大ヒットを記録。バンドの人気は最高潮に達することとなる。マイク&ザ・メカニクスの「ミラクル」の先にあるのは、バラバラに活動していたメンバーが、再びバンドを拠点にしてゆくという再生だった。別れを決意し、私邸を去ってゆく、ダイアナ、ウィリアム、ヘンリーの3人。奇遇なことに、ジェネシスのメンバーも3人なのだ。「ミラクル」を聴いているダイアナは、マイク&ザ・メカニクスの先にある、ジェネシスの更なる結束を知っている。映画の舞台となっている前月には、5年ぶりのアルバム「ウィ・キャント・ダンス」が発売されていたからだ。
【出典】
Mirror 2019.4.4 https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/princess-dianas-affairs-revealed-how-14234893
『スペンサー』©️Frederic Batier 『ダイアナ 世界を揺るがせた7日間』(c) Tim Graham/Getty Images+++
スター・チャンネル×映画.com
コラボ企画
【マニアックホラー沼へようこそ】
激レア傑作、大放出ゾンビ映画世界選手権も開催!
この夏、涼しくなりたきゃここに行きやがれ! ~観なきゃ損な作品紹介~
映画.com「スターチャンネルEX 激レア!ホラー&ゾンビ
2022」ページへ